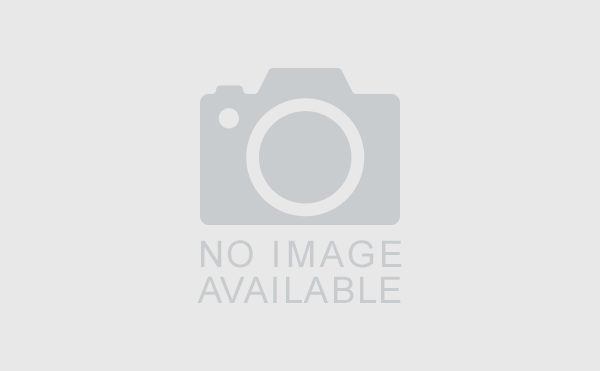ボルダリングを競技と捉える事の不正確さについて
私は浜松市でボルダリングを始めて11年、函館市でボルダリングジムのオーナーとなって6年目となっています。
時間的にも、オーナーという立場的にも、ボルダリングについて考える時間が長くなってきているのですが、最近は、
ボルダリングというものに対する世間のイメージは時々刻々と変化している、
という事を感じています。
これをお読みになっているあなたは、どれくらいボルダリングと関わり、ボルダリングについてどんな考えをお持ちでしょうか。
コンテンツ [非表示]
肥大化するボルダリングの競技としての側面
ボルダリングのオリンピック競技化や日本人選手の世界選手権での活躍などで最近強調されがちなのが、ボルダリングの競技としての側面です。
同じ国民が世界の舞台で活躍するという事は興味深く、誇らしい事ですし、素直に喜ぶべきこと事だと思います。
2020年に行われる東京オリンピックで日本人が金メダルを取れる可能性が高い競技ですので、注目を集める事は当然のことなのでしょうね。
こういったボルダリングを主に競技としてとらえている方は、ここ2,3年以内にボルダリングを始めた方や、子供にやらせている方に多い気がしていますが、私は、こういった見方は、正しくないと思っています。
競技として順位を競う事でしか自己を肯定できないクライマーは、コンペの上のクラスで勝てないと気が付いた時や、怪我や加齢などで勝てなくなってきた時に、ボルダリングと離れてしまうに違いありません。
しかし本来ボルダリングとはそんな薄っぺらいものではなく、生涯付き合っていけるような多面的なものなのではないでしょうか。
ボルダリングの文化的側面について
文化、という言葉は便利ですが、概念的にややぼんやりしていて否定も肯定もしづらい、形容した言葉がちょっといいイメージになる、ずるい言葉の様な気がします。
ですから私はボルダリングを形容する言葉としてあまり使いたいとは思わないのですが、やはりボルダリングは文化としての側面が大きいと思います。
まず、ボルダリングは元々、競技としての側面はありませんでした。
登山の様に、
単純に未踏の岩の上に自分が立ちたい
という欲求から生まれたものです。
そしてその欲求を認め、目の前の岩を登る楽しさが、多くの人の共感を得、魅了していったのだと思います。
つまり、基本は楽しいかどうかです。
具体的な要素を見てみましょう。ボルダリングは、
人間と対戦するわけでもなく、
タイムを競うわけでもなく、
登り方も人それぞれ認められ、
身長、体重別で課題が分かれている訳でもなく、
ただ無限にある組み合わせの課題を登る。
といった要素を持っていて、ボルダリングを愛好してきたクライマーはそれ自体を楽しんできました。
他者と競い順位付けを行う”競技”とは、随分かけ離れている事が分かると思います。
日本における”スポーツ”という言葉の意味について
どういうわけか日本では、スポーツは子どもの教育的価値観に寄った語られ方をされることが多いと思います。
実際ジムでも、自分ではなく子どもにボルダリングをやらせたい、というお客様は多いです。
子供にスポーツをやらせることで、体の発達、努力することの大切さの理解、成功する事の経験、協調性などの獲得を目的としているのだと思います。
それは間違いではありませんし、親心というものなのでしょうね。
しかし本来、
スポーツはそれ自体を楽しむもの、
ではないでしょうか。
ですから、それをやるのに大人も子供も無いのです。
ただ楽しめばいいのです。
この辺りの捉え方ついて日本は後進的だと思います。
欧米ではスポーツは教育的側面で捉えられることは少ないのではないでしょうか。
フランスのとあるボルダリングジムのカウンターには、ワインボトルが並んでいます。
夜な夜な酒を飲みながらボルダリング談義に花が咲いているのでしょうか。
きっとそのジムで登っているクライマーにとって、ボルダリングは酒等と同列の価値のもの、一生楽しむ事の出来るものなのでしょう。
話がちょっとそれました。
とにかく、私はボルダリングを競技やスポーツと思った事は一度もありません。
そして、私にとってのボルダリングも、ただ楽しいもの、です。
誰にもこの記事の考え方を押し付ける気はありませんが、
ボルダリングと長く付き合っていけるクライマー達と話していると、きっと同じように捉えているのだろうな、という気がしてなりません。